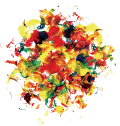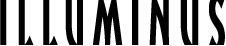写真家・須田誠が2007年に出版し、たちまち話題を呼んだた写真集「NO TRAVEL,NO LIFE」。須田のフィルターを通じ、私たちがまだ見たことのない世界各国の一瞬が収められたこの1冊は、老若男女を問わず、多くのファンを虜にしてしまった。
まるで生き字引のようにこの本を繰り返し眺めるファンは増大の一途をたどり、現在は写真集として異例ともいえる販売数(25,000部)を突破。31ヵ国もの国を巡った旅人でもある須田の原点ともいえるこの1冊が、Stage Project ILLUMINUSによって3度目の舞台化を迎えた。

“順風満帆な生活を送り、将来を有望視されていた須田誠は、積み上げてきたステータスのすべてを捨て、呼ばれるように世界放浪の旅へ出た。唯一の相棒は、「使い方も知らない一眼レフカメラ」”――。
「1/8000秒、世界はどのように映ったのか」
あらすじはこう結ばれていた。この世界を1/8000秒という単位で考えたことなど、果たしてこれまでにあっただろうか。
秋の空気が漂い始めた9月、千秋楽を迎えた池袋・シアターグリーン BASE THEATERに足を運んだ。
この舞台の大きなテーマを感じ取っているかのように、場内はワクワクとした笑顔の観客で満席となっていた。多くの人を、これほどまでに惹きつけられる「何か」が、やはりこの物語には溢れているのだろう。

ゆったりと吊り下げられたいくつもの白熱電球が優しい光を放つ中、多くの衣服や帽子、小物がステージの両サイドを飾っている。「旅をしている」…そのことが、一目でわかる見事な舞台美術だった。
期待を胸に幕開けを待つ。暗闇の中、カメラだけが照らし出されている。
しばらくすると、キャストがゆっくりと舞台へと登場した。続いて登場した「語り手」が、優しくストーリーを紡ぎ出す。
「語り手」を演じた宮澤が声を発した瞬間、凄まじいまでの引力によって、その世界がスタートした。動き、ふるまい、視線、歩き方…。物語の行く末をすべて知る「語り手」の宮澤は、まるで暖かく人を包み込む神様のようだ。
「世の中には、見えないけれど、触れないけれど、言葉に表せないけれど、だけど確実に存在する、ある大切なものがある…」
一瞬で心を捉えて離さない声に聞き惚れる。心が震えるとは、まさにこの事だろう。
「…写真は、その大切な世界と、人間世界の、ギリギリの世界に成り立つ、紙っペラ」
舞台はきらめくライティングと共に、オープニングを告げる音楽で包まれた。しかし、そこには不思議な感覚があった。


舞台のはずなのに、まるで映像作品を観ているような錯覚に陥るのだ。
新里が演じる主人公「須田誠」が旅先で「運命の一眼カメラ」を手に入れると、観客は時空を超えた時間旅行へと連れ出された。

就職した会社での風景、恋人との出会い、高校時代の面談、そして旅立ち――。物語は全体を通じて、主人公・誠の半生におけるいくつもの重要なターニングポイント、その中でもよりドラマチックなシーンを切り取って見せてゆく。時間通りに進むのではなく、なんと時間軸を行ったり来たりする。会社にいたと思えば、高校の校舎の中にいる。カフェにいたと思えば、旅先にいる。
主人公・須田誠を演じる新里は、その一瞬毎に大人になったり、子供になったりと、変化を全身で表現するのだ。

「映像作品を観ているようだ」というのは、これが理由だ。ドラマや映画のように、カットが次々変わってゆくのだ。
年齢を超え、場所を超え、時間を超える役者たち。特に主人公を演じている新里は、90分間、休む間もない展開の中にいる。
尋常ではないエネルギーがほとばしる。前半から、すでに全てを出し尽くすかのような熱演だ。
次々と変化が訪れるのは新里だけではない。谷、瀬尾、風間、三本、文夏の俳優5名は、一度も舞台から去ることなく、世界中の何役もの役を次々と演じてゆく。その演じぶりは、もはや「見事」としか言いようのないものだった。
誠の恋人役をはじめ、女性性の際立つキャラクターを多く担当していた谷。誠にとって「現実」を一番体現する恋人役において、その存在感を強く印象付けていた。誠のような生き方は理解できない…という人や、誠のような人が恋人だ…という人にとっては、谷のリアリティ溢れる演じぶりに、とても心を掴まれただろう。 誠の会社の同僚、友人など、誠にとって近しい同性の存在を中心に、様々な役を演じた風間。場内の空気を完璧に読み取り、自由自在に笑いや切なさを生み出していた。高い演技力だけでなく、お笑い担当にもイケメンにもなれるビジュアルも加わり、きっと本作以外でも多く活躍しているに違いない。 柔らかな雰囲気が魅力の文夏は、その明るく優しい笑顔で作品に彩りを添えていた。文夏が微笑むと、空気はほっと暖かくなる。誠の母役としても、深い愛情を感じる存在感を表現していた。たとえ叫んでいても、深みがあるのだ。

呆気にとられていた。全員、衝撃的なほど芸達者ぶりだ。
自分自身が、どんどん舞台へと引きずり込まれてゆくのがわかる。客席は、まるで宇宙にいるかのようだ。空から誠の世界を、ただただ夢中で眺めているような気分だった。
「ミュージシャンになりたい」という夢を諦め、「現実」を見て生活のために働く誠。しかし、そんな誠の日々を、運命が少しずつ動かしてゆく。
スクリーンに投影された時間軸が、過去と未来を行ったり来たりする度に、なんとか現実の重みを受け止めようとする誠の悶々とした葛藤を、身につまされる思いで見つめていた。
「自分を信じて、このまま生きてゆけばいいよ」――
「心の声」が誠を取り囲む。新里以外の5名の役者が、全員で囁くように「心の声」を表現していた。男女の声が混ざることで、それは「心の声」を忘れてしまった人々の、心の叫びのようにも感じられた。
悩む誠と解放された誠の対比は、そのまま日本と海外の対比でもあった。どちらが良くて、どちらが悪いというわけではない。ただただ「心の声」を無視できないでいる誠を、丁寧に表現してゆく新里の魅力が、更に開花してゆく。
過去、未来、日本、海外…場所や時間軸、様々に存在する場所を変えながら、誠は「心の声」と向き合ってゆく。大都会ニューヨークから、その日を生きることに必死な人々が暮らす小さな町まで、様々な人と出会い、カメラのシャッターを切る誠。

1/8000秒の瞬間が積み重なってゆく。
日本ではない国で、多くの答えを見つけながらも、誠は再び日本で会社員の道を歩んでゆく。しかも、順調に昇進し、順調に安定を手に入れる。まさに「順風満帆」で幸せで、恋人にも友人にも恵まれ、「こう生きるべき」というお手本のような日々…。
きっと世の中の大半の人は、この頃の誠のような生活を手に入れるために、毎日を必死に生きているに違いない。けれど、それは本当に「心の声」を聞いた上での答えなのか?
強力なメッセージが、強力に突き付けられてくるようだった。
導かれた旅先での誠は、まさに「水を得た魚」と言えるほど輝く瞳で世界を見つめていた。「ここは本当に劇場の中なのだろうか?」と戸惑うほどだ。様々な色を感じ、風をも感じられる。観客はこうして「心の声」に従って進んだ誠と共に、様々な時空へ運ばれてゆく。
誠と共に、悩んだり笑ったり、葛藤しながら旅をしているのだ。

「自由に生きてゆく」ことは、とても難しい。既に身動きすらも取れないほどに、「現実」にがんじがらめになってしまっている人もいるのだろう。けれどこの時、舞台の上で生きる誠を見つめながら、私たちは確かに旅をしていた。原作者である須田が「心の声」のままに生きてくれたことで、私たちは今、こうして旅ができているのだろう。
日本で、劇場の中で、椅子に座っているけれど、確かに世界を旅をしていた。吉田の脚本・演出は魔法を呼び起こした。時間軸を超える表現で、観客を旅へと連れ出したのだ。

この物語の中でも、最大のハイライトのひとつである「ロネルと家族」シーンは、見逃せない一幕だろう。2015年、10年ぶりにキューバを再訪した誠は、会えると思っていた友人・ロネルが刑務所に収容されており、3年に1度、数日間しか出られないことを知る。しかし、訪ねたその日こそが、その「3年に1度」の日だった。
ロネルを演じた瀬尾は、それまで卓越したコメディ・センスで笑いを巻き起こしながらも、このキューバ・シーンで、繊細でシリアスな一面を披露する。存分に笑わせてくれたからこそ、泣きの演技のギャップに魅了されてしまった。

そしてクライマックスは、瀬尾と三本、そして新里が作り上げるヒマラヤ遭難シーンだ。
「心の声」が、極限の世界を誠に突き付けてくる。ここは、再び吉田の飛び抜けた演出センスが伺える展開となっている。大きな白い布をはためかせることで雪崩を表現しており、ライティングと相まって恐怖の雪世界を作り出す。3人の演技力も最高潮に達し、息をのむような迫力が眼前に広がる――
ほぼ瀬尾と三本の独壇場ともいえるこのシーンでは、2人の飛び抜けた表現力が、観客をエベレストへと連れ去った。特に、三本の叫びや感情表現は、「死」を思わせながらも、この作品のトーンを悲しさに落としすぎない絶妙なバランスで繰り広げられていた。それは観客の気持ちを引き込むのに充分なもので、三本の凛とした美しさにすっかり魅了されてしまった。




ここで、新里以外の5名が演じる人々、そして物語の展開に共通するのが「誠を愛してやまない」ことであるのに気付かされた。
誠を取り巻く人々は、母であったり、恋人であったり、友人であったり、もう2度と会うことのない、旅先ですれ違う人であったり、または山の神、果てにはこの世界を作り出した創造神として、形の違う愛で誠を包んでいた。
誠はいつも、本人でも気付かないうちに、愛おしさをもって、この世界を見つめていたのではないだろうか。だからこそ、世界は誠に愛を返した。それが時には、受け止めきれないほどの厳しさであったとしても、それもまた、誠を「心の声」の道へ進ませるための、愛だったのではないだろうか。
きっとこれは、原作者である須田が、一番の相棒であるカメラを通じて見つめる世界、そのものなのだろう。
誠は「心の声」に従って、また旅立っていった。
ふと、新里がこの本を引き寄せ、この役を引き寄せた理由がわかる気がした。
新里がニッコリと嬉しそうに笑うだけで、世界が彼を愛してしまう理由となっていた。新里の笑顔や存在感には、そういう力があった。
清々しい涙が流れた。簡単な感動や悲しみによるものではなく、もっと深く、魂の奥から流れたような涙だと感じた。命とは、人生とは。そんな哲学的なことに、思いを馳せたくなってしまう。
ラスト、嵐を抜けた舞台奥の布が落ちると、そこには見事に額装されたいくつもの写真作品が登場した。


舞台の最後を飾るにふさわしい、説得力のある演出だった。原作者の須田による大きな数々の傑作写真は、「進んできた道は正しかったのだよ」と告げているようだった。
終了後には、原作者の須田と主演の新里による特別トークショーも行われた。それは2人の相性の良さが存分に感じられる微笑ましいものであると同時に、演じ切ったばかりの新里が舞台を去るギリギリまで、何度もお辞儀をしてゆく姿に思いやりが感じられた。更には須田も笑顔で観客と交流をしたりと、最後まで非常に暖かい気持ちになるエンディングだった。
今回で3度目の舞台化を迎えた「NO TRAVEL,NO LIFE」。多くの人の心を掴んで離さない傑作、再びの上演を期待したい。
池袋演劇祭エントリーしている本作品。まずはその結果が発表される11月に朗報を待とう。
【企画・構成:小宮山薫 取材・文:Murata Yumiko 写真:豊川裕之】